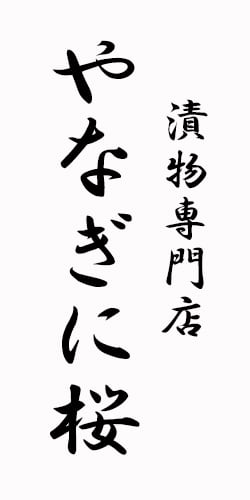2025/08/01 10:44
おはようございます。
先日のカムチャツカ地震による津波注意報で、一部地域に避難勧告が出されました。その際、「たった30cmの津波予想で避難なんて大げさだ」と避難した人を嘲笑する声があったと聞き、深い違和感を覚えました。命を守るための行動が、なぜ笑われるのでしょうか。
もちろん、津波予測の精度には限界があり、実際には大きな被害が出なかった地域も多かったのは事実です。しかし、そもそも津波予測には誤差がつきもので、「最大で50cm」などとされても、地形や潮位によっては予想を超えることもあり得ます。また、日本海側全域にわたって警報が出されるなど、範囲が広すぎて現実味が薄れ、避難勧告が空振りに終わるたびに「またか」と感じる人が増えているのも理解できます。
しかし、だからといって避難を選んだ人を笑っていい理由にはなりません。空振りだったとしても、「何も起きなかったこと」こそが成功なのです。避難が“無駄”だったのではなく、“被害が出なかった”から良かった。これは本来、社会全体で称賛すべき行動のはずです。
また、避難後に「警報は解除されないけれど警戒を続けて」といった曖昧なアナウンスだけでは、避難者はいつ戻っていいのか判断できません。このように防災行政の情報発信にもまだまだ改善の余地があります。
必要なのは、避難行動を“恥”ではなく“誇り”とする価値観です。避難した人が「空振りだったけど、ちゃんと行動できてよかった」と思えるような社会づくり。そうでなければ、次に本当に命の危険がある場面で、「また大げさだろ」と避難を躊躇する人が増えてしまう。最悪の場合、尊い命が失われかねません。
防災とは災害そのものを防ぐだけでなく、人々の判断と行動が尊重される社会をつくることでもあるのです。